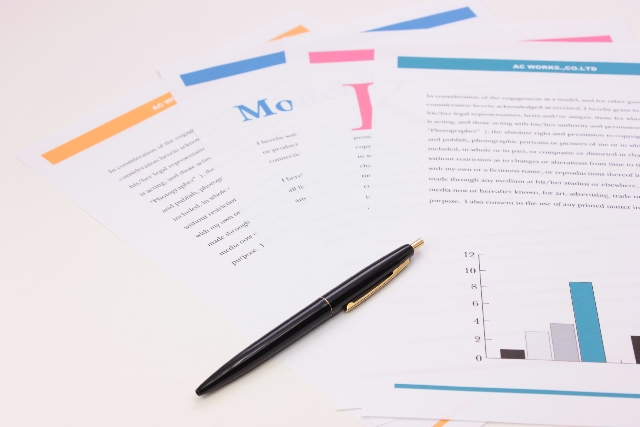


離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
〉診断書には4月1日と記載されています。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
住民税について教えてください。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
原則、今年度中に支給を受けた分が質問者様の所得となります。
源泉徴収票も今年中に受給した分のみで作成されると思います。
例として、給料を20日締めの25日払いの会社があるとします。12月20日~31日の未支給の給料を入れるのですか?と言っているのと同じです。
源泉徴収票も今年中に受給した分のみで作成されると思います。
例として、給料を20日締めの25日払いの会社があるとします。12月20日~31日の未支給の給料を入れるのですか?と言っているのと同じです。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
定年退職ということは、定年の定めがあり、その定めはハローワークに届出がされているはず。
定年退職の年齢に達しての退職は、雇用保険からすれば自己都合でも会社都合でもない、「定年」という離職理由であるはずですが、なにゆえに自己都合にして3ヶ月の給付制限をつけるのでしょうか?
思うに、会社内では60歳定年だと言っていても、規則が届出されていないのでしょうかね。
まあ、ハローワークは、強制力のある届出義務ではないからかもしれませんが。
管轄のハローワークで、職業安定分のなかで高齢者安定雇用の届出に係る担当に相談してみては?
「うちの会社、60歳定年で、定年退職を自己都合にするんです。まず、定年60歳を届け出していないのではないかと思います。それと、65歳までの高齢者雇用確保の制度を設けていないかもしれません。それって、違法ですよね。」
という感じでしょうか。
ただ、定年は解雇と違い、突然やってくるものではなく、予め準備しておけるものなんですよね。そういう点、定年がはっきりしていれば、そんなに手厚く保護される対象ではないですが。
不安なら、5年先のこと。どうとでも備えはできるのではないでしょうか。
定年退職の年齢に達しての退職は、雇用保険からすれば自己都合でも会社都合でもない、「定年」という離職理由であるはずですが、なにゆえに自己都合にして3ヶ月の給付制限をつけるのでしょうか?
思うに、会社内では60歳定年だと言っていても、規則が届出されていないのでしょうかね。
まあ、ハローワークは、強制力のある届出義務ではないからかもしれませんが。
管轄のハローワークで、職業安定分のなかで高齢者安定雇用の届出に係る担当に相談してみては?
「うちの会社、60歳定年で、定年退職を自己都合にするんです。まず、定年60歳を届け出していないのではないかと思います。それと、65歳までの高齢者雇用確保の制度を設けていないかもしれません。それって、違法ですよね。」
という感じでしょうか。
ただ、定年は解雇と違い、突然やってくるものではなく、予め準備しておけるものなんですよね。そういう点、定年がはっきりしていれば、そんなに手厚く保護される対象ではないですが。
不安なら、5年先のこと。どうとでも備えはできるのではないでしょうか。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
関連する情報